清八でございます。毎月、「食」に関する書籍・漫画・DVDなど、主に中古品を探しては買い求め、読んだり、観たりして学習しております。それでは10月分を報告させていただきます。
■NHK放送文化研究所世論調査部[編]「崩食と放食」日本放送出版協会(2006.12.10) 中古本
:
2006年3月1日から19日まで、全国の16歳以上3600人対象に配布用紙に記入していただく方法で、現代の日本人がどのような食生活をしていて、食についてどのような価値観をもっているかについて調査された、貴重なレポートでした。
39~75頁の第Ⅱ章「飽食のなかの放食~食へのこだわりのなさ~」に興味を持ちました。「‥こうした特徴を合わせてみると、食へのこだわりがあるか、それとも無頓着かという違いが浮かび上がってきます。そして、若年層で無頓着な人が多いという傾向があることがわかります。若年層、特に男性は一日三食ではなく、健康への配慮をすることも少なく、空腹を満たせばよいと考える傾向が強くみられます。こうした食へのこだわりの弱さ、食に無頓着な傾向を『放食』と表現してみました。‥こうしたデータはもちろん、朝食をとらなかったから食生活に満足できないという原因と結果の関係ではありません。朝食をとらなかった人やふだんから一日三食をきちんととろうとは考えていない人で、満足していない割合が高いという傾向があるということです。それは『一日三食をきちんととる』ように心がけている人は、食生活全般について気をつけていて、そうでない人よりも質の高い食生活を送っているので、食生活により満足しているのだと考えられます。‥」
農学博士の高橋久仁子さんからの提言です。「‥そう、誰もが自分てせつくってみればよいのです。お父さんもお姉さんも高校生の息子も、調理を担当するみとです。家族全員が生活者として煮炊きする。食の崩壊、食生活の乱れをあげつらう前に、自分で煮炊きして、自分の食を取り戻すことです。そこから確実にみえてくるものがあります。‥」(画像①)
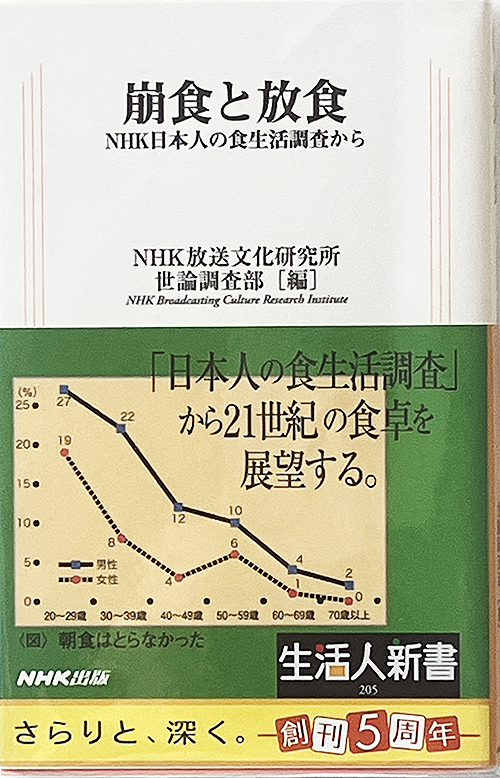
(画像①崩食と放食)
■永山久夫著「古代食は長寿食」保育社 (1993.4.30) 中古本
:
30年以上前の出版物でしたが、古代人の食生活、調理法が書かれていて面白い読み物でした。14~25頁の「縄文式 食治法の知恵」の中に、ゴボウが「ガン予防食」として書かれていました。「‥縄文人は、スジばかりのゴボウをなぜ栽培していたのだろう。森の住民である縄文文化では、肉食比率が高かったとみられている。肉といっしょに煮込むこことによって、肉の臭気ょ消し、ゴボウ自体にも肉の味がよくしみこんだのである。‥ガンやコレステロールなどの成人病を防ぐ効果の強いリグニンは、切り口からたくさん発生するという特性がある。なぜ、切り口や傷口からリグニンが増加するかというと、ゴボウ自身が細菌から身を守るため。縄文人は、ゴボウを叩くことによって、ガンを防ぎ成人病を防ぐ“薬”を作っていた。‥」
48~55頁の「『魚』は頭もよくなる長寿食」では、和食文化と魚について書かれていました。「‥日本に、江戸時代の末期まで『肉食文化』が根を下ろさなかったのは、仏教の影響も、もちろんあるが、魚が豊富にとれ、しかも古代から独特の『大豆文化』が発達していたため、それだけでタンパク質は十分にとれ、肉はあまり必要でなかったからである。日本人は、この島国で、『米』を主食として、『魚』と『大豆』でタンパク質を補給し、『野菜』でビタミンやミネラル、センイ質をとるという、風土の産物を利用する独自の食文化を形成してきた。‥日本の『長寿村』は、山間部にもあるが、圧倒的に多いのは海辺か海に近い所であることも、魚の重要性を物語っているのではないだろうか。‥」(画像②)
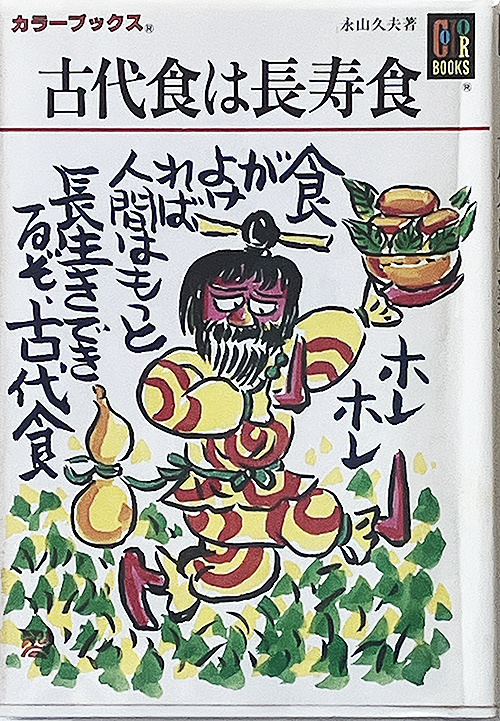
(画像②古代食は長寿食)
■池波正太郎著「そうざい料理帖 巻一」平凡社 (2011.1.7) 中古本
■池波正太郎著「そうざい料理帖 巻二」平凡社 (2011.1.7) 中古本
:
2003年と2004年に平凡社から刊行された「池波正太郎のそうざい料理帖」の文庫本でした。以前にもこのコラム内で書かせていただきましたが、私は池波正太郎の愛好者で文庫本で全点購入し、読破してきました。テレビ化、映画化された作品も全部観てきました。そして、食生活や食エッセイに書かれたお店や料理にも関心を持ってきました。この二冊には、作り方のヒントがイラスト付きで描かれていて、それはそれは愉しい読み物でした。巻一の79~82頁は「茄子の胡麻油風味焙り焼き」でした。「‥俗に、『秋茄子は嫁に食わすな』という。秋茄子があまりにうまいので嫁に食べさせると切りがないという姑気質をさしたものだとされているが、実は、茄子の食べすぎは女体を損うことを案じてのことらしい。漬物もよいが、私は夏になると小さな焜炉へ金網をのせ、二つ割りにした茄子の切口へ胡麻油を塗って焙り焼きにし、芥子醤油でやるのが好きだ。このときは冷酒を湯のみ茶わんでのむ。‥」
104~107頁は、「一夜ソース漬けカツレツ」でした。「‥母の月給日の夜は、子供ごころに待ちかねたものだ。つとめの帰りに、母がカツレツを買って来てくれるからだ。このカツレツを、私は三分ノ一ほど残しておく。ソースをひたひたにかけて‥。翌朝、このソース漬けになった薄いカツレツを熱い飯に乗せて食べるときのうまさといったら、こたえられないものだった。‥」
巻二の62~64頁は「豆腐の小咄-冷奴二品」でした。「‥江戸時代の小咄に、『豆腐は栄養があっておいしいが、一つの難がある。それは、あまり値が安すぎるんらばかにされるのだ』というのがあるが、それもいまは夢物語となってしまったようだ。‥」
冷奴二品の一品目は、日本代表で「氷水に浮かべ、生醤油で。薬味は紫蘇と晒葱」。二品目は、中国代表で「豆腐半丁に、干海老を戻したものを刻み、ザーサイと葱のみじん切りを合わせ、醤油、酢、ごま油で和えたものをのせる。」(画像③)

(画像③そうざい料理帖)
■堀和久著「江戸風流『食』ばなし」講談社 (1997.3.17) 中古本
:
江戸期庶民の食と薬に関する雑学エッセイで、川柳と小話のオンパレードでした。
21~31頁は「鰻が変じて山の芋」。「小話‥和尚が俎板に、生臭の最たる鰻をのせて、包丁を取り上げたところへ、ひょっこり檀家が顔を出し、目をむく。和尚、少しもあわてず、首をかしげ、『はてさて、不思議なことがごじゃる。昔より、山の芋は年を経れば鰻に変ずるともうすのを虚説であろうと凝っておったが、ごろうじょ、山の芋を吸いものにしようと思っていたら、みるみる鰻になってしまった』」「‥鰻料理の店には、大抵、どじょうがメニューにある。どじょうは、鰌、泥鰌、鯲の字をあてる。紺ののれんに『どぜう』と染め抜いた専門店もある。なにゆえ『どぜう』か。食べ物商売の縁起かつぎで偶数文字をきらうことと、とくに四(死)文字を避けたことが理由とされている。‥」
189~202頁は「豆腐百珍」。「小話・その二。『小僧や、横町の豆腐屋へ行ってな、御亭主に、ちょっとお出なさいませ、と言ってきなさい』『アイ、それで、どこでございます』『はて、鈍なやつだ。あの豆腐滓(おから)屋のことですか』『ばかなやつ。きらず屋というものがあるか』『それでも、わたしは、きらずばかりを買いに行かされます』
「‥田楽は、本来、豆腐のみであった。だが、次第にこんにゃくや里芋の田楽も現れるようになった。江戸は、赤味噌仕立てで、串は一本。上方はも白味噌を用いて、串は二本。しかし、必ずしも統一されていたわけではない。江戸でも二本ざしの白味噌田楽はあった。『二本ざしが怖くて、田楽が食えるか』という啖呵は、町人の武士へり向こう意気である。‥」(画像④)
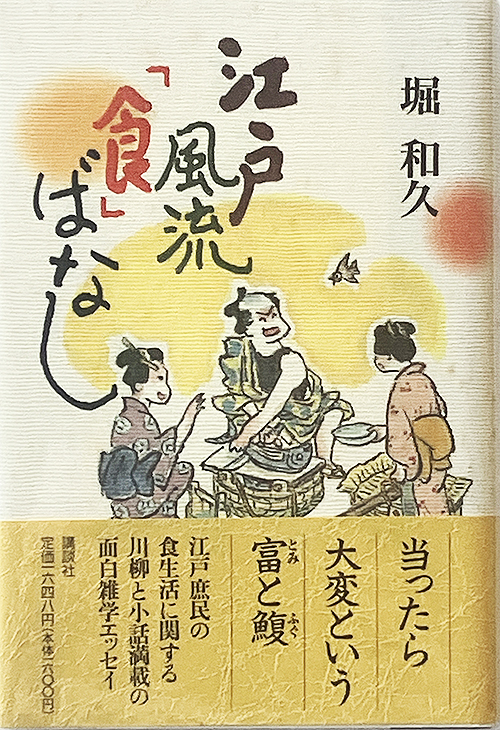
(画像④江戸風流『食』ばなし)
10月17日、浜松市のシネマイーラさんで「風のマジム」を観てきました。9時30分上映で観客18人でした。原田マハ原作、主演が伊藤沙莉、祖母を高畑淳子、母を富田靖子、バーのマスターに染谷将太、伝説の醸造家に滝藤賢一など脇を固め、芳賀薫の映画初監督作品でした。南大東島で地元のサトウキビからアグリコールラムをつくる話なんですが、悪人は一人も登場しない、ほっこりとした内容になっていました。
実は、このラムは2005年に拙宅での「わいわいワイン会」計画中に、高山の坂本酒店さんから教えられて、取り寄せ、参加メンバーで試飲した記録が残っていました。先ほど、Perplexityで調べたら、南大東島ラム「COR COR(コルコル)は、会社設立が2004年、生産開始がその後まもなく、最初の製品発売は2005年頃と教えてくれました。と、いうことは私達が試飲したのは、まさに最初のラムだったのです。実は、この映画のエキストラには沖縄在住の妹の旦那で出ていて、今回は招待券をいただきました。いろいろな事がつながって嬉しい2025年10月となりました。(画像⑤)

(画像⑤風のマジム)
2025.11.27 清八
