清八でございます。毎月、「食」に関する書籍・漫画・DVDなど、主に中古品を探しては買い求め、読んだり、観たりして学習しております。それでは7月分を報告させていただきます。
■木村俊介著「料理狂」幻冬舎文庫 (2017.4.15) 中古本
:
裏表紙に書かれている「内容紹介?」には、「1960年代から70年代にかけての、いわゆる『日本の外食業界』の青春時代に、人生を賭けて異国で修行を積んだ料理人たちがいる。奴隷労働のような量の手作業を何十年間もこなし市場を開拓し、グルメ大国日本の礎を築いた谷昇、鮎田淳治、佐竹弘、野崎洋光、音羽和紀、小峰敏宏、田村良雄、田代和久。彼らの肉声から浮き彫りになる仕事論とは。」
インタビュアーである筆者が、菓子職人、支配人、各種食材業者も含め25人からの肉声をまとめられたインタビュー集であり、その店舗の一見客には聞かれたくないような内容も収録されていました。
東京・麻布十番で1982年からイタリア料理店「LA COMETA」のオーナーシェフを務めている鮎田淳治氏は1951年生まれで、イタリアで8年間修業されています。「‥いまじゃ笑い話だけど、1975年にイタリアに渡った直後というのは、エスプレッソの苦味が強烈で、毎回、気分が悪くなってたんです。蜂の巣や骨髄や内臓の料理もそそうだった。‥言葉もそうだね。結局、ある特定の文化の中に入ってなじむってすごいことですよ。逆に言えば、最初はいやいやでも自分のほうから異文化に入り込まないと永遠になじめないと思う。その文化のよさって、現地になじまないとわからないの。‥」
東京・青山で1986年からフランス料理店「ラ・ブランシュ」のオーナーシェフを務めている田代和久氏は1950年生まれで、28歳から3年間フランスで修行されています。「‥信頼って義理とか人情とかの世界の話だから、相手に信頼されるような努力をしなければ得られないものですよね。こういうことを言うと若い人は暑苦しいと思うかもしれない。でも、若いならいくらでも見栄を張ってもいいし恥をかいてもいいけど、義理と人情はなかなか取り戻せないものなので気を付けてね、とは言っておきたいんですよ。若い料理人なら、技術を高めるのと同時に、料理に対して努力するぶんの一割でも二割でもいいから、人に信頼されるための努力をしたら、つまり、おいしすぎる話には乗らないで、地道に我慢していくことを重ねたら、運って来るんじゃないのかな。‥」
私と奥様は、浜松市のフランス料理店「エピファニー」にはオープン早々から通わせていただき、豊橋市のイタリア料理イン「フラスカティ」には20年近く通っております。コロナ禍も含めて固定客が増えない(失礼)頃に、何度もオーナーシェフと奥様と私達のみの空間で修行時代のお話を聴かせていただけました。書けないことの方が多いのですが、宝物のように私の頭の中の引き出しに詰まっております。本当に、ありがとうございました。(画像①)
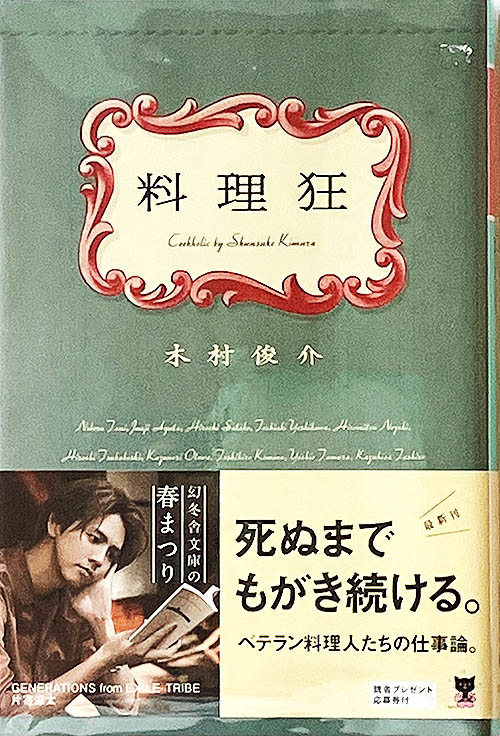
(画像①料理狂)
■梛木春幸著「フランスで大人気の日本料理教室」(2020.9.1) 中古本
:
食育日本料理家として食育の講演活動、商品開発、地域活性化事業、仕出し、食品加工、料理プロデュースなどを行う株式会社樹楽代表取締役による講演や料理教室で話されてきた日本料理についての「うんちく」本でした。
61頁の「お寿司の定番に付けられた江戸時代ならではの粋な呼び方」では、「‥『かっぱ巻き』と言えば、胡瓜の巻物です。かっぱ(河童)の好物が胡瓜という話から、そう呼ばれるようになりました。『鉄火巻き』は鮪の赤身の巻物、鉄を火で熱すると真っ赤になることや、花札やサイコロなど、バクチをする場所のことを「鉄火場」と呼び、そこで手軽に食べられていたことから、『鉄火巻き』となりました。鉄砲巻きは、山葵を効かせて炊いた干瓢を入れた巻物です。筒状の形が鉄砲に似ていることや、山葵を効かすので、食べたときに鉄砲に撃たれたような顔にゆることから、『鉄砲巻き』と呼ばれるようになったと言われています。‥」
80頁の「海の魚を使った料理なのに『田作り』と呼ばれる理由」では、「‥江戸時代、豊漁だったときの鰯の余りを、干してイリコ状にして田んぼにまいたところ、お米が驚くほど豊作になったことから、鰯は高級肥料として使われるようになったそうです。また、海の魚を使った料理なのに、『田作り』と呼ばれるのは、このため、そして、田植えのころに、豊年豊作祈願で鰯を食べる習慣が生まれました。‥」
165頁の「漢数字の『一』のように盛る。すると、旦那が出世する」では、「‥漢数字の『一』を書くように真ん中を小高くする『一文字盛り』という盛り付け方があります。これは裏千家の茶懐石で、炊きたてのご飯をまずひと口お出しするときの作法のこと。これを取り入れて、料亭などでもそのように盛り付けられることがあり、俗説として『人文字盛りをすると旦那が出世する』などとも言われています。‥」(画像②)
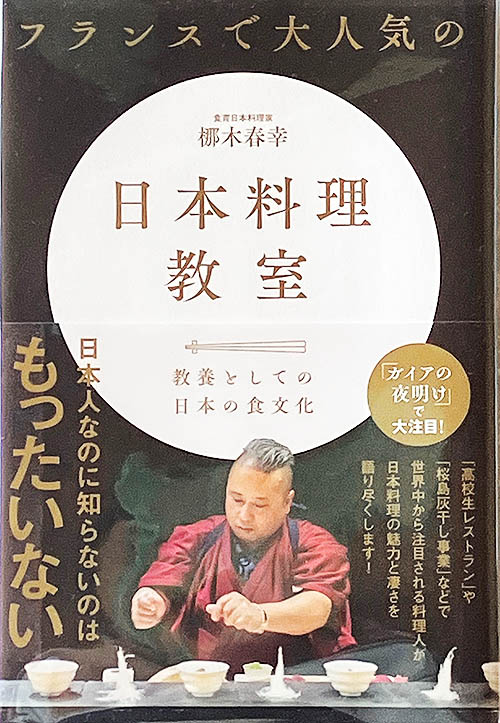
(画像②日本料理教室)
■角田光代著「彼女のこんだて帖」 講談社文庫 (2016.3.16) 中古本
:
月刊「ベターホーム」の2005年4月号から2006年3月号に掲載された、料理を作ることと男女、友人、知人の物語で「レシピつき連作短編小説集」の一冊でした。料理とレシピですが、「ラム肉のハーブ焼き」「そら豆のポタージュ」「野菜と生ハム、パルミジャーノのサラダ」「中華ちまき」「ミートボール入りトマトシチュー」「かぼちゃの宝蒸し」「ぬか漬け」「タイ風焼きそば」「タイ風さつまあげ」「タイ風オムレツ」「春巻きスティック」「ピザ」「手打ちうどん」「かけうどん」「松茸ごはん」「スノーパフ」「豚柳川」「餃子鍋」「手作り餃子」「あじといかの一夜干し」「たらとほうれんそうのグラタン」「きのこマーボー」「春菊とほたてのスープ」「五目ちらし」「蛤のお吸いもの」「菜の花とささみのからしあえ」が取り上げられていました。
タイ料理が登場する短編の舞台は、新大久保駅裏手のタイ料理屋でした。毎月一回、食同好会メンバーのリクエスト料理を提供してくれるレストランで、アラカルトで注文して、確認しながら食べ歩く。食材、調味料をあげながらレシピを書き、わからないものは書店の料理本コーナーで立ち読みしてレシピを完成させる。そしてメンバーに招待状を出して、その日に自分で全員分を調理して、全員で料理とお酒を楽しむ、といった会であった。(画像③)
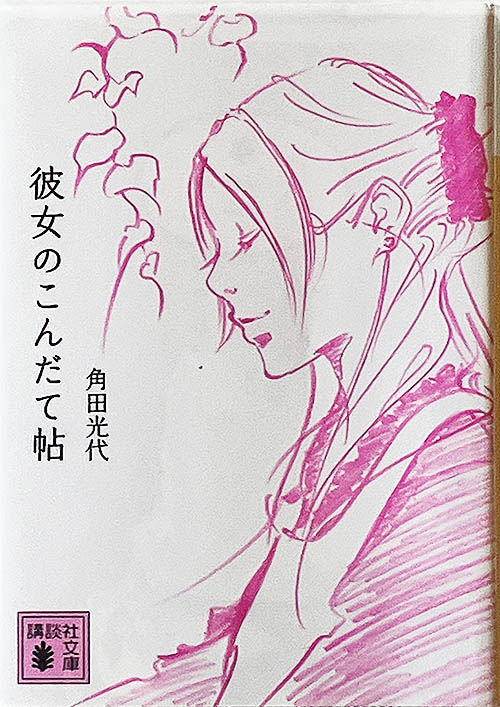
(画像③彼女のこんだて帖)
■「暮しの手帖 37 夏」暮しの手帖社(2025.7.25) 新刊本」
:
38~47頁に「ヨーロッパで出会った味 ワインさんの多国籍料理で夏のおもてなし」。長野県松本市のデリカテッセン「欧州料理Kawazoe」を営まれているワインあけびさんの紹介と彼女がつくるイタリア・フランス・チェコの料理とレシピがくわしく掲載されていました。北イタリア・エミリアロマーニャ州の小さな村のレストランの賄い「トマトのヴェルッタータ」。プラハのレストランで出会った「グリルしたレタスとハーブのサラダ」。イタリア・ピエモンテ州の郷土料理「カルビオーネ」。パリで食した「ヘーゼルナッツのペストのカスクルート」。チェコの夏のお菓子「ベリーのブブラニナ」。もうすぐにでも松本市のお店に飛んでいきたい気分にさせてくれました。
96~103頁は「旬を味わう一汁三菜 稲田俊輔の新おそうざい十二カ月」でした。八月のお品書きは「ズッキーニと豚肉のしょうが焼き」「夏野菜の揚げびたし」「トマトともずくの土佐酢」「海苔とわさびの小吸いものふう」「ご飯」でした。九月のお品書きは「なすと鰹のたたき」「厚揚げ納豆」「しめじみそ」「冬瓜そぼろ汁」「里いもご飯」でした。鰹の刺身はもう65年近く食してきて、20年位前からは「たたき」にしてワインの肴にしてきました。みょうがだったり、青しそだったり、貝割れ大根、玉ねぎを合わせたりしてきましたが、このレシピでは秋ナスの斜め切りをサラダ油で軽く両面を焼いて「たたき」と重ねて並べてから、ポン酢醤油をかけるやり方でした。一度、トライしてみようと思いました。
120頁の「暮らしのヒント集」に、こんなヒントが掲載されていました。「いいことがあったら、少額でも寄付をしてみましょう。『お福分け』が、きっと誰かに届きます。
(画像④)
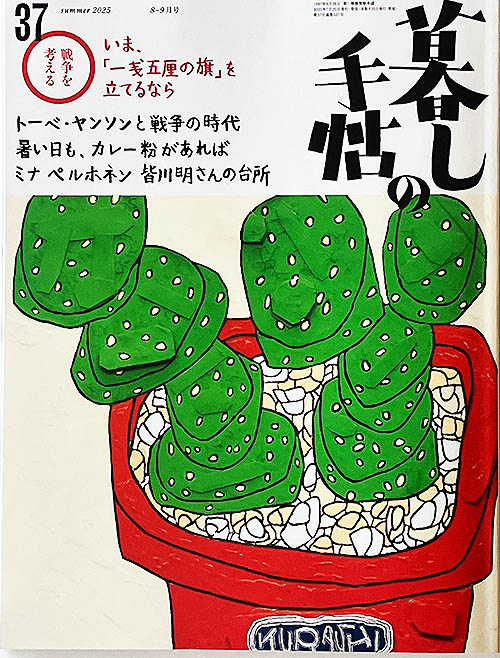
(画像④暮らしの手帖)
■椎名誠著「あやしい探検隊 北海道乱入」角川文庫 (2014.10.25) 中古本
:
2011年に刊行された単行本「あやしい探検隊 北海道物乞い旅」の文庫本でした。
第三次あやしい探検隊「雑魚釣り隊」のメンバー8人による北海道極貧物乞い旅の書下ろしレポートなのですが、8人で9日間の北海道旅行を74万円(そのうち角川書店から50万円)の予算の為、飛行機ではなく、大洗から苫小牧までカーフェリーを利用して2台の自家用車で廻りながら、昼食以外は現地食糧調達という計画でした。それが、それが、室蘭の三角ペースの仲間に会ったとたん、「おぼろづき(米)」30キロ、高級清酒、米焼酎、珈琲焼酎など12本、値段にして33,860円を差し入れ。テント泊に頼んだ静内の「藤沢牧場」では牧場主から、サッポロクラシックビール5ケース、おたるワイン24本、生ビールをサーバー付、ニュージーランド産のラム肉4キロのご提供。その夜のバーベキューパーティには室蘭からの遊び仲間5人が「施し物」を積んで到着した。「クロソイの刺身」「カジカ汁」「毛蟹11パイ」「ソウハチガレイの干物(いっぱい)」「室蘭ヤキトリ(といいいつつ豚肉)どっさり」「室蘭カレーラーメン(20人前)」「うずらのプリン(40個)」、さっそく食べきれずに食材としてストックできた。
厚岸の宿泊場所となった番小屋では、地元の漁師さん達から、「焼き牡蠣」「牡蠣汁」「クチグロのチャンチャン焼き」「アサリ」、そして缶ビール、ウイスキーのボトル‥次から次への大宴会、大接待大会。いやはや、酔いどれオヤジたちによる行き当たりバッタリの「あやしい探検隊」の旅でした。本当に面白かったです。(画像⑤)
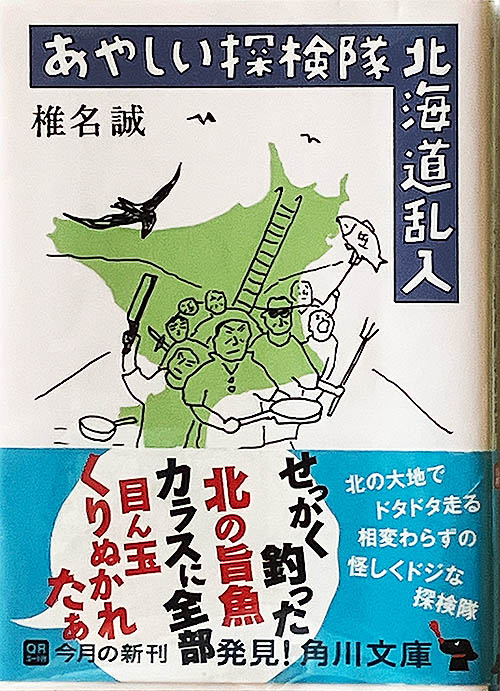
(画像⑤あやしい探検隊)
■「Mac Fan 2025.9」マイナビ出版 (2025.7.29) 新刊本
:
私が、このコラム「ちりとてちん」に書かせていただいてから、もう22年になるのですが、初めてアップル社の雑誌を取り上げます。実は、アップル社製品とは45年間の付き合いになってます。1977年から1988年まで、私は地方公務員として当時の新居町役場で働いておりました。1980年頃だったと思いますが、当時の新居町史編纂室に愛知大学の教授と学生さん達が働いておりました。興味があって昼休みに伺うと、全く見たこともないパソコンがありました。当時のMacintoshのコンピューターでした。その後に、「漢字Talk」というソフトが登場して、日本語入力ができるようになったのですが、80年には英語入力のみでした。どうして、英語入力で町史編纂に利用できるのか教授に伺ったら、論文は英語で作成するから英語入力でかまわないというご返事でした。こうして初めてのMacintosh製品に出会い、当時の西武百貨店・浜松店の7階にあった専門店にも通い、個人的に教えていただいてました。Macintosh SE、Power Macintosh、Power Mac iPod、iPad、iPhoneと使い続けてきました。フロッピーディスクは処分しましたが、1992年の「Macintosh 日本語入力操作ガイド」は保管してありました。(画像⑥)
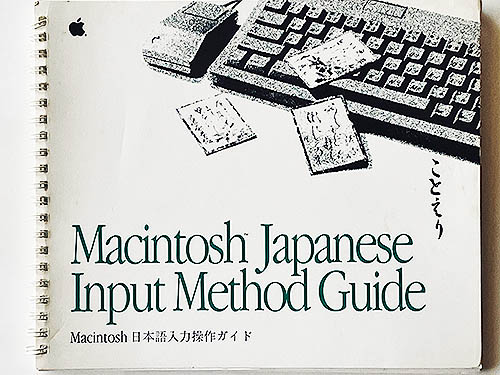
(画像⑥日本語入力操作ガイド)
さて、この号の92~93頁に「医療とApple」という掲載記事があり、「飲料大手のキリンが作る健康支援アプリ『WellWa』の本気と勝算」とありました。これまで様々な「健康支援アプリ」が登場していますが、有料の法人向けのアプリなのだそうです。個人的には利用できないのですが、同社内でのデータ分析によると、
「‥つまり、健康習慣やコミュニケーションの改善によって、従業員の仕事に対する『活力』『熱意』『没頭』などの心理状態が向上し、出勤しているにも関わらずパフォーマンスが上がらない状態が解消されることが示唆されたる‥」おそらくは、Z世代を含めて「健康管理」をアナログでは管理できない時代になっていることは間違いないのです。(画像⑦)

(画像⑦Mac Fan)
2025.8.28 清八

