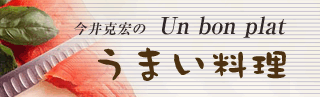
|
うまい料理を食べることは、人生最良の一場面といえる。 人生を料理に賭けてきた「三鞍の山荘」の今井克宏シェフが語る「Un bon plat」アン ボン プラ(うまい料理)。食卓や料理の話題を取り上げてもらいます。 |
「総あがり」
|
コック見習いには見るもの全てがめずづらしかった。 フォン(出し汁)には魚、とり肉、牛肉と種類があることも少しずつではあるが分かってくる。 このフォンからソースがつくられることも「贅沢なんだな」と感心しながら覚えていった。 今のように調理師学校に行き1年間、または2年間の勉強をしてあらゆる知識を分かった上で調理場に入って来るのとはわけが違うのである。中学校を卒業したばかりの自分には、まったく未知の世界だった。 昭和29年ごろは一般 の食生活はまだ洋風化はされず、田舎育ちの自分にとっては洋食はカレーライスだけが唯一食べた洋食であった。ハヤシライスを食べたのも東京に出てきてからだ。 叔父の家がある小石川で、近所の洋食屋から出前を取り食べさせてくれたのが始めてのデミグラスとの出会いであった。林(ハヤシ)さんが作ったのが最初でこの名前がついたのだということもこの時聞いて、これをずっと信じていたのである。見習いになってから大きな「ナべ」の中にデミグラスがふつふつと煮立っているのを見て「みそかな」……と思いつつ「ナメ」てみて「へえ、これがあのハヤシライスの素か……」ついでに「林さんが作ったハヤシライス」はおいしいですね…と先輩に声をかけたが相手にしてくれなかったのでそれからもずっと「林さんのハヤシライス」を信じていた。18才からフランス語を習うようになり「アッシェ」きざむという言葉を知った時から「アッシェ、ドウ、ブフ、アベック、デュ、リ、」すなわち発音的にアッシェがハヤシに変化していったことを知った。ずいぶんと長い間「林さんのハヤシライス」を信じていたことになる。
調理場での仕事が慣れるにしたがって先輩たちには派閥があることに気がついた。ホテルから来た人たちとアメリカの進駐軍から来た人たちとが反目しあっていたのである。小さないさかいは日常茶飯事でいつ「バクハツ」するかわからなかった。ボイラー係の人と板前がケンカをして、ナイフを持ったボイラー係が逃げる板前を追っかけていったのもその前兆であった。和食の調理場は2階にあったので全館を逃げまわったことになる。止める人もいないので不思議に思いつつどうなるのかと不安な私の前を二人はかけぬ けていった。やがて仲直りをしたのか二人は逃げまわったコースを逆もどりしていった。この時はもうナイフはケースの中に収められ板前の方が持っていたのだから「どうなってるの……」。こんな争いを見ていると、とてつもない職場にいることに気がつきだした。 自分の気持ち次第で良くも悪くもなる職場であった。新しくきた料理長が支配人の頭をフライパンでなぐりつけ「オイ、ヤメタゾ」とどなると2番さんから下の先輩たちが料理長についてぞろぞろと調理場から出ていった。残ったのは派閥の違う進駐軍あがりのコックたちだけが「オレタチ、カンケイナイネ」という顔をして、イモの皮をむいていた。退社届けがフライパンの一振りとは恐れ入ったが、シャレている場合ではない。見習いコックはどちらについていけばよいのか迷っていると支配人が頭を抑えながら「お前は残れ」そして私の耳元で「新しいシェフがくるから心配するな」…ということだった。 次の日には、ヒゲをたくわえた料理長と四人のコックがやってきた。これを入れ替え、または“総あがり”といって、そっくり調理場のメンバーが替わってしまうというのだ。驚いている暇はなく、洗い場は自分のことでいっぱいでメンバーがかわっても「ナべ」が変わらない限り洗い方は一緒である。新しいコックたちとのコミュニケーションは磨き上げた「ナべ」を見たとたん「オメーヤルネー」「イクツダ」「ソ‥カ、ガンバレヨ」と洗い物を誉めてくれたのが最初だった。ヒゲの料理長はフランス語がペラペラであった。自分が何も分からないからペラペラとコラ、ソラ、トレ…と何でもラとレがついているので「すげーや、料理人は外国語が話せなければならないのだ」とまた新しいことに気がつくのであった。フランス語は分からないので、聞き惚れているしか方法がないが、進駐軍からきたコックたちは、やたら英語をしゃべった。イエスとウイとノンとノーが乱れとんでいる。栃木の田舎から出てきて東京の街にショックを受けているのに、さらに仕事と言葉である。 調理場は相変わらず不穏な毎日であったが、洗い場にとってはめずらしい料理をつくっているのを見ることができ、面 白みはあった。ただ、いつ「バクハツ」するか分からぬ戦場にいるようで、「バクダン」のまわりをウロウロしているような気分でいたのは事実だった。 二派に別れている職場は、メニューによってそれをどちらが作るかで決まっているようだ。例えば、オムレツは進駐軍派が受け持っている。気をつけてみるとカツ丼、親子丼、トンカツ、カキフライ、エビフライ、オムライスなど洋食屋さんで作られるものが全て進駐軍派であった。とはいえ、カレーライス、ハヤシライスなどソース類のものは、対ヒゲのシェフ派が作っているようだ。ヒゲのシェフ派は宴会料理をやっていて、今までに見たことのない料理が多かった。冷蔵庫の中にも塩漬けにした豚バラや豚ロース、牛舌などが入っていたり、ソミュール液に漬け込んだ鮭などもあった。いずれも、これに触ったり、のぞいたりすることは御法度で、ヒゲのシェフ派だけの管理になっていた。見せてくれないとなると、見てやれという反逆精神の持ち主でもあるので片っ端からナメまくってみた。確かに塩辛いが、それぞれに味が違っていることに興味をもった。やがて、その一部がオードヴルの皿にのっているとこれもまた感激である。洗い場の特権は、内緒ではあるが、味を見ることが出来ることである。ソミュール液の中に浮かんでいた葉っぱが月桂樹の葉であることに気がついたり、ゴミのようにうかんでいたものがローズマリーであったり、スパイスというものがこうして使用されるのかと思うと、大変な発見をしたようで心臓が飛び出すほどコーフンしたのである。 ところが一ヶ月もしないうちに、ヒゲのシェフ派は「総あがり」をしたのである。原因は何であるか分からないが、ある朝、突然にあれほど大事に仕込まれていた肉や魚や、内臓などの材料が冷蔵庫からひっぱり出されるとギャベジ缶
の中に滅茶苦茶にほうり込まれたのである。すなわち、捨てられたのである。そして「総あがり」の決まった「セリフ」を残して一行は去って行ったのである。わずか一ヶ月とはいえ、一緒に働いたのであるから自分も仲間に入れてくれれば良いものを冷たいものであった。捨てられたものに未練があって、とりだして食べてやれとチャンスを伺ったが、まわりの雰囲気が荒っぽかったので、とてもそこまでの勇気が出ないうちにギャベジ缶
を「豚屋」さんに持って行かれてしまった。 |
||||

